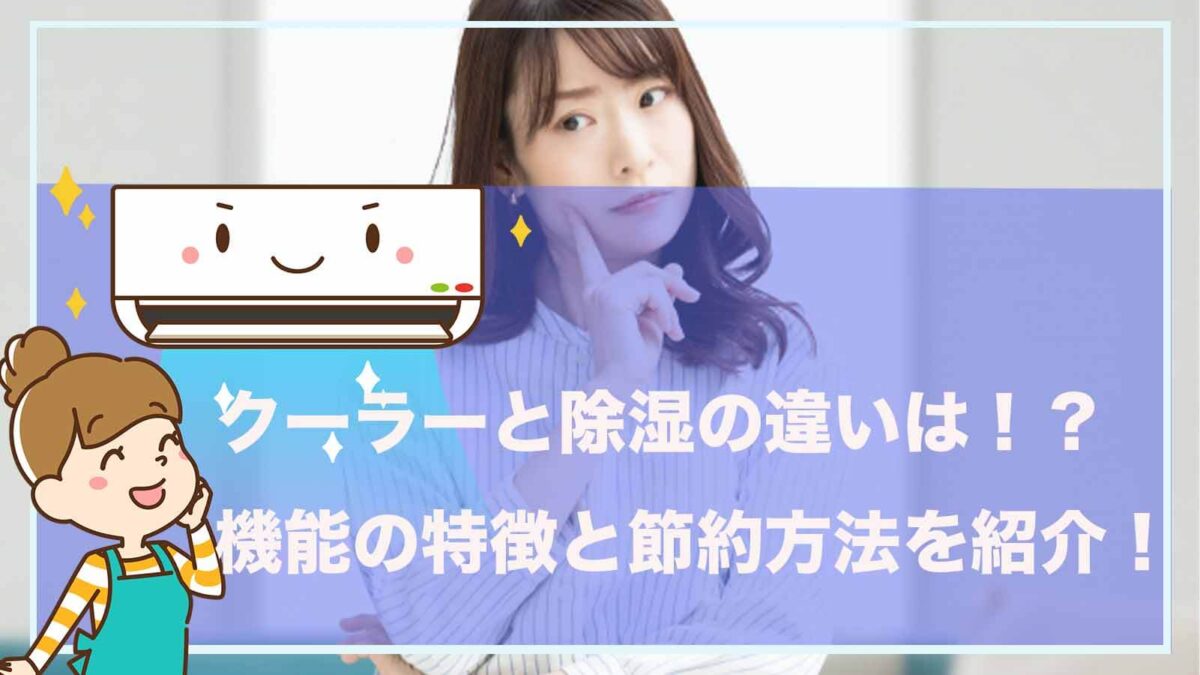- クーラー(冷房)と除湿の違い
- クーラーと除湿の使い分けのポイント
- 電気代の節約方法
エアコンのクーラー(冷房)と除湿は、暑さから快適な室内環境を作ってくれる機能です。
ですが、それぞれの機能には仕組みや使用目的が若干違ってきます。
夏の暑さを和らげるためにクーラーを使う人が多い一方で、湿度が高いときに除湿機能が活躍するケースもあります。
しかし、機能の違いをしっかり理解していないと、効果的な使い方ができないことも。
この記事では、クーラー(冷房)と除湿の基本的な違い、使い分けの方法や節約方法などについて詳しく解説していきます。
適切な知識を身につけることで、より健康的で快適な室内環境を作れるようになります。
 エアコン清掃clubの滝沢
エアコン清掃clubの滝沢私は、【エアコン清掃club】を運営する滝沢というものです。ハウスクリーニング業者で約5年ほど従事した経験をもとに記事を書いています!
クーラー(冷房)と除湿の違いとは?


エアコンの「クーラー(冷房)」と「除湿」は、一見似たように感じられるかもしれません。
ですが、それぞれの仕組みや役割は大きく異なります。
快適な室内環境を整えるためには、まずこの2つの機能の違いを正しく理解することが大切です。
クーラー(冷房)の特徴と使用場面
クーラー(冷房)は、エアコンが冷たい風を送り出すことで”室温そのものを下げる”運転方法です。
冷媒が室内の熱を吸収し、外へ排出することで空気を冷やしてくれます。
気温が高い夏場においては、効率的に室温を下げてくれるため、暑さ対策として非常に効果的です。
ただし、湿度はあくまで間接的に下がるだけで、除湿を目的とした運転には適していません。



「体感的な涼しさ」を優先したい時におすすめです!
除湿機能の特徴と使用場面
除湿モード、いわゆるドライ運転は、”湿度を下げる”ことに特化した運転です。
エアコン内部で空気を冷却し、湿気を水滴として取り除く仕組みですが、必要以上に冷やさずに済むのが特徴です。
肌寒さを感じにくく、梅雨時や夜間など、気温がそれほど高くない場面でも快適に使えるモードです。
実はエアコンの除湿機能には種類がある


一言で除湿といっても、その方式は一つではありません。
エアコンによる除湿には複数の種類があり、”湿度を下げる”という部分は同じですが、それぞれに特徴と利点、注意点があります。
使用環境や目的に応じて適切に選ぶことで、より効率的に快適さを得られます。
弱冷房除湿
一般的に「除湿」と言われるのがこの弱冷房除湿です。
部屋の空気を取り込み、水分を除いてから部屋に戻すことで除湿を行います。
室温の大きな変化を避けつつも、湿度だけを下げたい場合に便利です。消費電力が比較的少なく、静音性にも優れているため、就寝時の使用にも向いています。
しかし、設定温度より室温が低いと作動しにくく、除湿効果が薄れることもあります。



効果を引き出すには、室温と設定温度のバランスに気をつける必要があります!
再熱除湿
再熱除湿は、湿気を取り除いた後に空気を再加熱して室温を保つ仕組みです。
このため、除湿しながらも肌寒さを感じにくく、快適な室温をキープできます。
特に、湿度が高いけれど気温が低い時期や時間帯に効果的です。



ただ、再加熱の工程により電力消費が増える点には注意が必要です!
クーラー(冷房)と除湿の使い分けのポイント


温度を下げるクーラー(冷房)・湿度を下げる除湿。
この2つの機能をうまく使い分けることで、電気代を抑えながらも快適な空間を保つことが可能です。
使用シーンごとに最適なモードを選択することが、効率的なエアコン運用の鍵となります。
- 真夏のピーク時は冷房を優先する
- 朝晩の涼しい時間帯は除湿運転を活用
- ムシムシした梅雨など【除湿がおすすめ】
- 風通しの悪い部屋【除湿がおすすめ】
- 部屋干しの洗濯物には除湿が効果的
- 長時間不在時は省エネモードで運転
真夏のピーク時は冷房を優先する
気温が30℃を超えるような猛暑日には、室温そのものを下げる冷房モードが必須です。
除湿運転だと室温があまり下がらず、蒸し暑さを感じやすくなってしまいます。冷房でしっかりと温度管理をすることで、熱中症のリスクも軽減できます。
設定温度は26〜28℃前後、風量は「自動」にしておくのが使い勝手も良いでしょう。



風量の自動はエアコンの節電対策としても有効です!
朝晩の涼しい時間帯は除湿運転を活用
気温が25℃以下まで下がる早朝や夜間は、除湿(ドライ運転)が適しています。
冷やしすぎずに湿気だけを取り除くため、肌寒さを感じさせず快適に過ごせます。
また、寝苦しさを解消しつつ電気代も節約できるため、睡眠時には特におすすめです。
心配な方は、タイマーで就寝開始から数時間だけ動かす方法もあります。
ムシムシした梅雨など【除湿がおすすめ】
梅雨の時期は室温こそ高くないものの、日本の梅雨は湿度が80%を超えることも珍しくありません。
温度が高くなくても湿度の高さから不快に感じる方もいるでしょう。
除湿なら、肌寒さを感じずにカビ抑制効果を得たい場合に最適です。
健康面や部屋のコンディションを優先するなら十分に価値があります。
風通しの悪い部屋【除湿がおすすめ】
風通しの悪い部屋の場合、除湿が効果的です。
もちろん、真夏のような高温の場合は、クーラーでないと部屋は涼しくなりません。
部屋干ししている室内・クローゼットの湿気といったものも、除湿を使うと湿気を取ることができます。



部屋のジメジメ感がなくなるだけでも、気分的には違ってきます!
部屋干しの洗濯物には除湿(ドライモード)が効果的
洗濯物を部屋干しする場合、除湿で効率よく乾燥を促せます。
結露を利用して湿気を集める仕組みなので、部屋全体の湿度も下がってカビ予防にもつながります。
クーラーより電力消費が少ないため、夜間や在宅時の部屋干しにぴったりです。
長時間不在時は省エネモードで運転
外出や留守中にエアコンを切ってしまうと、帰宅時に再度フルパワーで冷やす必要が出てきます。
省エネ(エコ)モードにしておくと、一定の温度を保ちながらムダな運転を抑えられます。
設定温度を28℃前後にしておけば、帰宅後の快適性を大幅に損なわずに済みます。



帰宅直前にタイマーでクーラー(冷房)に切り替えるのも賢い方法です!
クーラー(冷房)と除湿で電気代の違い


クーラー(冷房)と除湿の違いや特徴がわかっても、電気代は気になります。
しかし、残念ながらこの部分に関しては、温度や湿度、環境によって違ってくるため一概に言い切ることは難しいです。
ただ、純粋な電気代だけでいけば【冷房>除湿】となります。
もちろん、真夏の暑い日に除湿だけを使っていてもなかなか快適な温度にすることは難しいです。
そのため、余計に電気代もかかってしまい、単純に室内の冷やせるクーラーの方が節約できます。



室内の環境・状況にあった機能を選ぶのがベストです!
クーラー(冷房)と除湿での電気代の節約方法


最近は物価高の影響から電気代も上がっています。
そのため「エアコンに使う電気代はなるべく抑えたい!」という方もたくさんいるでしょう。
運転モードだけでなく、日常的な使い方や設定次第で電気代は大きく変わる可能性もあります。
次のポイントを押さえて、無駄なく省エネを実現しましょう。
- 頻繁に電源のオンオフをしない
- 設定温度を調整して消費を抑える
- 扇風機やサーキュレーターと併用
- 室外機の周りはものを置かない
- 定期的なエアコンクリーニング
- 断熱対策でエアコン負荷を削減
- タイマー機能や留守番機能を使う
頻繁に電源のオンオフをしない
「電気代の節約」というつもりでも、エアコンの電源のオンオフを頻繁にするのは要注意です。
エアコンの使用で電気代がかかるのが、「電源を入れてから設定温度に達するまで」です。
一度、電源をオフにすれば設定温度からは離れていくだけでなので、またオンにすれば電気代が多くかかります。
もちろん、消している期間や時間帯などによっても、「つけっぱなしじゃない方がお得」というパターンはあります。



就寝中につけっぱなしを選択する場合には、室内の乾燥状態にも気をつけましょう!
設定温度を1℃ずつ調整して消費を抑える
クーラーでは、設定温度を1℃下げることで約10%の電力削減が期待できます。
暑さ寒さを我慢する必要はありませんが、快適な範囲で設定温度を見直すことが省エネへの第一歩です。
こまめな調整で体感温度を維持しつつ、無理なく節約しましょう。
扇風機やサーキュレーターと併用する
扇風機やサーキュレーターなどとの併用は電気代の節約につながります。
エアコンと併用することで体感温度が下げられるため、設定温度を高くしても快適なままです。
また、空気の循環もしやすいため、部屋全体を効率よく冷やすこともできます。
設定温度を控えめにしても体感温度は変わらず、結果として消費電力の削減につながります。



換気のシーンでも扇風機・サーキュレーターは大活躍です!
室外機の周りはものを置かない
室内の風は室外機を通って外に出ます。
そのため、室外機周辺にはものを置くのは避けましょう。
室外機周辺が汚れていると冷暖房効率が下がるだけでなく、ゴミなどを吸い込むことで故障の原因になることもあります。
定期的なエアコンクリーニングをする
エアコンは、「室内の空気を吸い込み風を送り出す」仕組みのため、フィルターや内部に汚れが溜まりやすいです。
フィルター・内部にホコリや汚れで詰まっていると、空気の流れが悪くなり、冷暖房効率が下がってしまいます。その結果、設定温度に達するまでの時間が長引き、余計な電力を消費します。
また、エアコン内のダニやカビなどを放置することで、アレルギーなどの健康被害をもたらす可能性も。
【フィルターなら2週に1回程度】【内部クリーニングなら1年1回程度】を目安にしましょう。



フィルター掃除は自力でも可能ですが、エアコンクリーニングはプロに任せるのがベスト!
窓・ドアの断熱対策でエアコン負荷を削減
窓からの日差しやドアの隙間からの外気の流れは、室内温度を乱す大きな要因です。
遮光カーテンや断熱フィルムなどの使用は、エアコンの負荷を軽減してくれます。
結果として運転時間が短くなり、電気代の節約に直結します。



特に夏場の日差しが差し込む窓や玄関周りなどは優先的に対策しましょう!
タイマー機能や留守番機能を賢く使う
睡眠時や外出時はタイマーやおやすみモードなどの機能を活用することで、不要な運転を防ぎ、効率的な温度管理が可能になります。
例えば、就寝後に徐々に設定温度を緩めることで、無理のない省エネが実現できます。
こうした機能をうまく取り入れることで、快適さを損なわずに電気代を抑えられます。
エアコンクリーニングの必要性と依頼のポイント
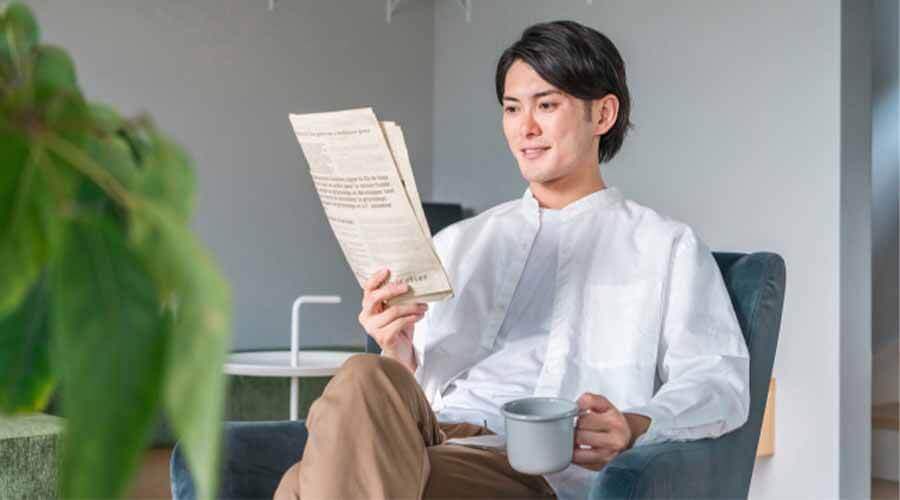
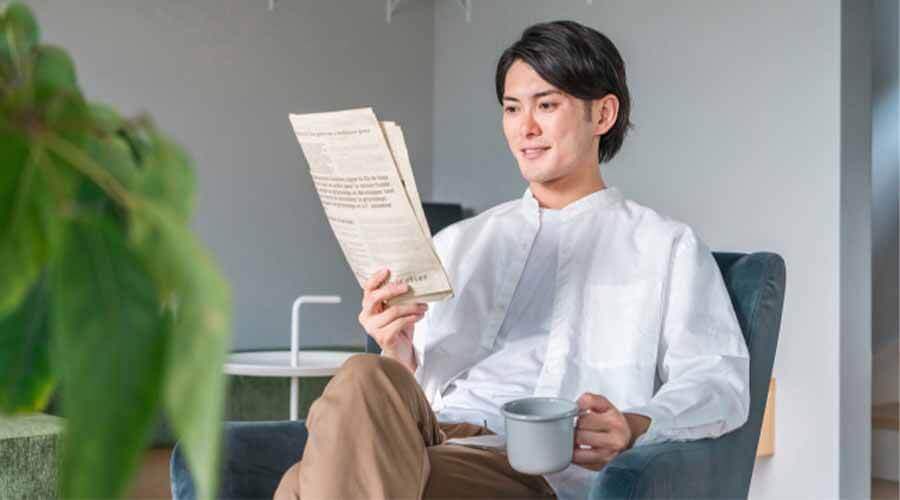
「エアコンから臭いがする」「風が弱くなった」と感じたら、それは内部の汚れが原因かもしれません。
安心してエアコンクリーニングを依頼するためにも、必要性や注意点を押さえておきましょう。
汚れがもたらす健康リスクと臭いの原因
エアコン内部にはカビやホコリが蓄積しやすく、それがクーラーや除湿時に吹き出し口から部屋中に広がります。
特に除湿モードでは結露が発生しやすいため、カビの温床にもなりがちです。
このカビやホコリは、アレルギーや喘息の原因になることもあるため、健康面のリスクを避けるためにも定期的な清掃が欠かせません。



「エアコンの風が臭い!」という場合も原因も同様に、カビや汚れが関係しています!
プロに安心して依頼するためのチェックポイント
エアコンクリーニングの依頼が初めての方は、「どこまで掃除してくれるの?」「追加料金は発生しないの?」などを不安に感じるかもしれません。
依頼前に業者のホームページの確認や見積もりを依頼することで、作業範囲や料金体系を確認できます。
エアコンクリーニングにはトラブルが発生してしまうケースもあります。念の為に補償内容(例:水漏れや部品の破損など)などもきちんともチェックしましょう。
SNSや評価サイトなどの口コミや施工実績も重要な判断材料になります。



全国展開の業者の場合、地域・担当者によって評価が変わることも!
クーラーと除湿について:まとめ
この記事では、クーラー(冷房)と除湿の基本的な違い、使い分けの方法や節約方法などについて詳しく解説してきました。
クーラーと除湿は、それぞれ目的が異なる機能であり、適切に使い分けることで快適な生活環境を作ることができます。
暑い夏の日にはクーラーで室温を下げ、梅雨時期や湿気の多い日には除湿機能を活用するなどが理想的です。
また、扇風機やサーキュレーターなどを併用することで電気代を抑えつつ、室内の快適さをさらに高めることもできます。
自分の住環境や体調、エネルギー消費のバランスを考慮して使い分け、より健康的で快適な室内環境を実現しましょう!